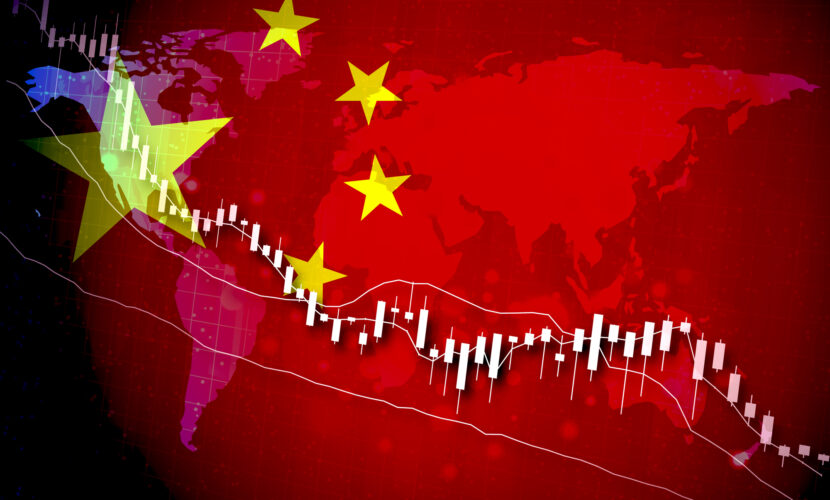日本企業、とりわけ中小規模の事業者にとって、中国EC市場は今なお魅力的な成長フロンティアです。
日本製品に対する品質・安全性への信頼は根強く、「良いものを正しく届ければ、きっと売れる」という希望は自然なものです。
しかし実際には、そう簡単にはいきません。言語や文化の違いだけでなく、販売チャネルの構造や顧客の購買体験への期待値、現地で必要となる人材や法的手続きまで、そのすべてが“別のゲーム”といっても過言ではないほどです。
本稿では、中国EC市場を初めて目指す中小企業に向けて、どのように準備を進め、何に注意し、どういうステップで着実に立ち上げていけばよいのかを、実務の視点から解説いたします。
日本から見える「信頼」と、中国で求められる「体験」のギャップ
まず知っておくべきは、中国の消費者が日本製品に対して強い信頼を抱いている一方で、ECサイトそのものの利用頻度はそれほど高くないという現実です。
つまり、商品そのものは信頼されていても、購買体験が期待に達していないために選ばれていない、という構造的なギャップが存在しています。
中国のECユーザー、とりわけ都市部の若年層は、購入前にSNSでレビューを検索し、気になった商品はライブ配信で試し、購入後は「すぐ届き、すぐ返品できる」ことを前提に買い物をしています。
このような「体験主導型」の消費文化に対応するには、日本企業側も、自社の商品だけで勝負するというよりも、その商品が“どう語られ、どう試され、どう応答されるか”までを含めた全体の設計が求められます。
越境ECと現地法人、どちらから始めるべきか
中国市場にECで参入するには、大きく分けて二つのルートがあります。一つは「越境EC(クロスボーダーEC)」、もう一つは「現地法人を通じた国内ECプラットフォーム参入」です。
越境ECは、日本国内の在庫を活用し、個人輸入として中国の消費者に商品を届けるモデルで、比較的手軽に始められる点がメリットです。
一方、Tmall本店やJD(京東)といったメインストリームのECモールに本格出店し、スケールのある展開を狙うには、中国国内に法人を設立し、現地での諸手続きを踏まえた上での参入が求められます。
中小企業にとっては、まずは越境ECを通じてテスト販売を行い、市場の反応やオペレーションの適応度を見た上で、現地法人化を検討するという「段階戦略」が現実的かつ成功確率の高い進め方と言えるでしょう。
商品と物流の準備は、規制理解から始める
越境ECといっても、商品がどのように税関を通り、どのルートで届くかによって、必要な書類や手続きは大きく異なります。
たとえば、保税区を経由して中国国内から発送する「保税モデル」と、日本から直接個人宛てに発送する「直送モデル」では、スピード・コスト・規制対応の内容がまったく違います。
また、化粧品や健康食品などは、販売前に中国国家薬監局(NMPA)の登録が必要となるケースもあり、事前にHSコードを確認し、該当する法律・規制を整理しておくことが欠かせません。
越境ECの税制は、通常の輸入と比べて簡易的な課税制度が適用されるため、個人消費を想定した販売であれば、比較的低リスクで始められます。
ただし、この枠組みに乗るには「越境EC指定プラットフォーム」や「通関番号の取得」など、一定の登録が必要になるため、最初の段階で専門家のアドバイスを得ることをおすすめします。
成功を左右する“語られる設計”と現地人材の力
中国の消費者は、購入の際に必ずといっていいほど、SNSやショート動画、KOL(インフルエンサー)のレビューを参考にします。これはもはや宣伝ではなく、文化の一部です。言い換えれば、「語られていないブランド」は、存在していないも同然なのです。
そのため、自社のブランドや商品の「語られ方」までを戦略として設計することが必要不可欠です。
たとえば、小紅書(RED)で誰にどう語らせるか、動画でどのように使用シーンを演出するか、WeChatで顧客との継続的な関係をどう構築するかといった点は、売上に直結する重要項目です。
このような運用には、中国市場に精通した現地パートナーや中国語ネイティブの人材が不可欠です。
初期段階では、現地のEC代行企業(TP=タオバオパートナー)に店舗運営やカスタマー対応、KOLマッチングなどを委託する形が多く見られます。
将来的に法人を設立し、自社で採用・育成する道もありますが、まずは信頼できるパートナーを通じて、運用ノウハウを得ることが最も現実的でしょう。
法人設立・手続き・許可:現地参入のハードルは高い
中国国内で本格的な事業展開を行う場合は、会社設立が必要になります。具体的には、工商登記、銀行口座開設、法人代表の任命など、日本の会社設立よりも煩雑で時間を要するプロセスが伴います。
また、ウェブサイトの運営にもICP備案という制度があり、公式サイトを中国国内で開設する際には当局への事前登録が求められます。
商品によっては個別の許認可(たとえば医薬品・化粧品に関するNMPA登録など)が必要になるため、参入業種ごとに法規制の確認が必須です。
とはいえ、こうした手続きを一度にすべて進めようとする必要はありません。
越境ECを通じた小規模な販売テストから始め、現地の反応を確かめつつ、段階的に投資とリスクを拡大していく方法が、リソースの限られた中小企業にとっては最も合理的なアプローチとなります。
最初の一歩は「中国語の翻訳」ではなく、「文化の翻訳」から
最後に、最も重要な視点を一つ。
中国市場を狙う際に、中小企業が陥りやすいのが「とりあえず翻訳して売ってみる」というアプローチです。
しかし、現実はもっと複雑で、単なる言葉の翻訳ではなく、文化的な期待と体験の翻訳こそが鍵を握ります。
返品文化、SNSでの語られ方、購入プロセスにおけるスピード重視の感覚、ライブ配信に求められる温度感―こうした全体の流れを理解し、“その国の消費リズム”に製品とサービスを合わせていく姿勢がなければ、本当の意味での定着は難しいでしょう。
私たちはこれまで、多くの企業とともに、中国市場への進出に携わってまいりました。市場調査の設計から、SNS運用戦略、現地パートナーの選定、講演・社内研修に至るまで、貴社の状況と目的に応じた支援が可能です。
はじめの一歩をどう踏み出せばよいか。迷われている段階でも構いません。まずは、自社の「語られる価値」は何か、という視点から一緒に整理してみませんか。